●この記事では、『原料・原産地表示の「輸入」表示の意味』についてお伝えしています。
食品を購入するときに、「表示変わった?」と感じるときはありませんか?
端的に言えば、原産国の表示が細かくなったと思いませんか?
今回は、「2017年からすでに始まっている加工食品の原料原産地表示制度」についてご紹介します。
輸入大国「日本」ならでは?
そもそもの話しですが、日本の食料の約6割は海外からの輸入に頼っています。
そんな「日本ならでは」と言えるのかもしれませんが、消費者庁の調査では「約7割の消費者が、食品の商品選択時に原料原産地名の表示を参考にする」と答えています。
こういった事情があり、「加工食品の原料原産地表示制度」が始まりました。
ちなみに、これまでも原材料の産地表示は、一部の加工食品にのみ義務づけられていました。
ですが、2017年9月からは全ての加工食品の1番多い原材料について、原料原産地が義務づけられました。
→経過措置期間は2022年3月末まで。
ただし、この原料原産地表示の意味を知らないと勘違いすることになります。
原料原産地表示で勘違い?
単純に考えれば、「産地表示があるのだから、どこの国から輸入された商品か一目で分かるのでは?」と思いますよね。
ですが、表示の意味を知らないと間違えて解釈する可能性があります。
原料原産地の表示方法は以下の5通り
- 製品中、最も多く使われた原材料が生鮮食品の場合は、その原産地を表示(国産の場合は「国産」である旨を表示)
- 2か国以上の原産地の原材料を混ぜて使っている場合は、多い順に原産地を表示
- 3か国以上の原産地の原材料を混ぜて使っている場合は、3か国目以降を「その他」と表示することも可能
- 製品中、最も多く使われた原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示
- 原則の「国別重量順表示」が難しい場合は、一定の条件のもと、「又は表示」、「大括り表示」の表示が可能
このように、食品表示の記載の基本は「最も多く使われている順番」です。
ただし、対象は「日本国内で製造または加工されたすべての加工食品」です。
つまり、「輸入した加工食品」・「外食」・「作ったその場で販売する食品(店内で調理された惣菜や弁当)」・「容器包装に入れずに販売する食品」などは、対象外になります。
*輸入した加工食品は、輸入した国(原産国)の表示が義務づけられている。
これが、「加工食品の原料原産地表示制度」のだいたいの概要です。
つまり、私達は加工食品を購入するとき、「原産国の表示がなされた輸入した加工食品」と「日本国内で製造・加工された加工食品」を選択していることになります。
それでは、日本国内で製造された加工食品の表示で、どういった勘違いが引き起こされるのでしょうか?
原料原産地名の勘違い!?
例えば、子ども達が大好きなウインナーは豚肉が使われていますよね。
この豚肉の原料原産地名が「アメリカ」とあれば、豚肉の原産地は「アメリカのみ」となるため、分かりやすいですよね。
仮に、原料原産地名に「カナダ産・アメリカ産・その他(豚肉)」とあっても、先程説明した通り多く使われている順番に記載されていることが分かります。
ただし、「その他」と記載があるため、それ以外の産地のものも使われていることになります。そのため、抵抗がある人もいるかもしれません。
ただ、ここまではまだ分かりやすい法です。
*ちなみに、「原料原産地名」としなくても、「原材料名:豚肉(アメリカ産)」・『枠外に「原料豚肉の原産地名」:アメリカ産』といった表示でも問題ない。
それでは、これが例えば「りんごジュース」ならどうでしょうか?

りんごジュースの場合は?
りんごジュースには、基本的に「りんご果汁」がはいっていますよね。
それでは、「りんご果汁(ドイツ製造)」と書かれていた場合、あなたはどのように解釈するでしょうか?
- りんご果汁がドイツで作られた?
- りんご果汁に使われたりんごがドイツ産?
→答え.りんご果汁がドイツで作られた。
つまり、これだけではどこで作られたりんごを使用したか分かりません。
さらに言えば、例えば、原材料の加工食品が国内で作られた物は「国内製造」と表示されますが・・・
→「その加工食品に使われた生鮮食品の産地が、国産」であるという意味ではない!
つまり、それぞれ別々に考えなくてはいけません。
また、「原材料名:りんご果汁」と記載があり、原料原産地名:ドイツ産(りんご)・ハンガリー産(りんご)とある場合もあります。
この場合は、りんご果汁に使われたりんごは「ドイツ産とハンガリー産のみ」で、さらに「ドイツ産のりんごを多く使っている」という意味になります。
原料原材料表示としては、こちらの方がより詳しく親切だといえるでしょう。
このように、原料原材料に自信があれば「日本の加工食品」として厳選した食材を選んで食品を作っていることが、ブランドとしてアピールすることもできます。
とはいえ、必ずしも重量を正確に表示できるとは限りません。
国別重量順に表示できない場合?
例えば、先程のウインナーの場合、原材料の調達先が変わったり、使用量の順番が変わったりといったことが引き起こされることがあります。
こういった場合、国別に重量順に表示することが難しくなりますよね。
こういった時に、そのウインナーに使われていた豚肉が、アメリカ産とカナダ産だったとすると、原料原産地名などに、「アメリカ産又はカナダ産」と表示することができます。
ただ、逆に言えば「それ以外の国の豚肉は使われていない」ということになります。
ですが、注意が必要なのは「大括り表示」の場合です。
「大括り」ってどういうこと?
実は、3ヶ国以上の外国の原産地を「輸入」と括って表示することができます。
先程のウインナーを例にすると、「輸入(豚肉)」と表示することができてしまいます。
さらに言えば、3ヶ国以上の外国産を混合してなおかつ国産の豚肉も使用していた場合は・・・
→「輸入、国産(豚肉)」といった表示になる。
この場合、国産も含めれば「4ヶ国以上の豚肉を混ぜて作られたウインナー」ということになります。
ちなみに、「輸入、国産」と言うことは、「輸入の方が国産よりも使われている」という意味です。
また、どちらが多く使われているか判断することが難しい場合は、「輸入又は国産」という表示になっています。
今回紹介した「原料原産地表示」は、まだ移行期間中です。
2022年3月末までに順次、表示が切り替わっていくため今のうちに表示の意味を理解できると新しい食品表示を生かすことができるでしょう。
少なくとも、「輸入」が3ヶ国以上の原材料を混ぜて作られていることは、知っておいて損はないでしょう。
そして、「その他」と記載があればどこの国の原料などが使われているかは分かりません。
*「輸入」・「その他」と記載があれば、原産国不明という落とし穴がある。
最後に
原料原産地表示は、あくまでも「日本国内で製造または加工されたすべての加工食品」のみが対象です。
もちろん、「国産が絶対安全」と言うつもりはありません。
本来なら、どこの国の輸入品であっても安心して食べられれば、わざわざ「原料源産地表示」がなくてもいいでしょう。
とはいえ、やはり不安に思っている消費者が多いことが現状です。
ちなみに、厚生労働省「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」によれば・・・
東京都の平成26年度違反調査結果では、国産の違反が0.07%、輸入食品が0.07%で、違反率は同程度
という結果が紹介されています。
また・・・
中国で日本へ輸出される食品は、土づくり、ほ場、運搬、製造、出荷まで工程ごとに厳しく管理されている。中国国内で流通する食品(中国の基準に従うもの)とは、別のもの
とも記載されています。
ただ、そう言われても私自身どこまで信用していいのかやはり不信感があります。
本来は、少しでも安全な食品を食べたいのであって「●●産だから食べたくない」では目的が変わってきていますが、どうしてもこれまでの経緯を考えると・・・
そういう意味では、国内も例外ではなく、福島県産の風評被害はいまだにあります。
少なくとも、日本での食品の取扱いは厳しい基準によって取り扱われていることは間違いありません。そのため、私達の国産に対する信頼が高いことは間違いないでしょう。
今後も、食費表示の透明性は大事ですが、今後は事実に基づいた輸入品のイメージ改善も必須になるでしょう。









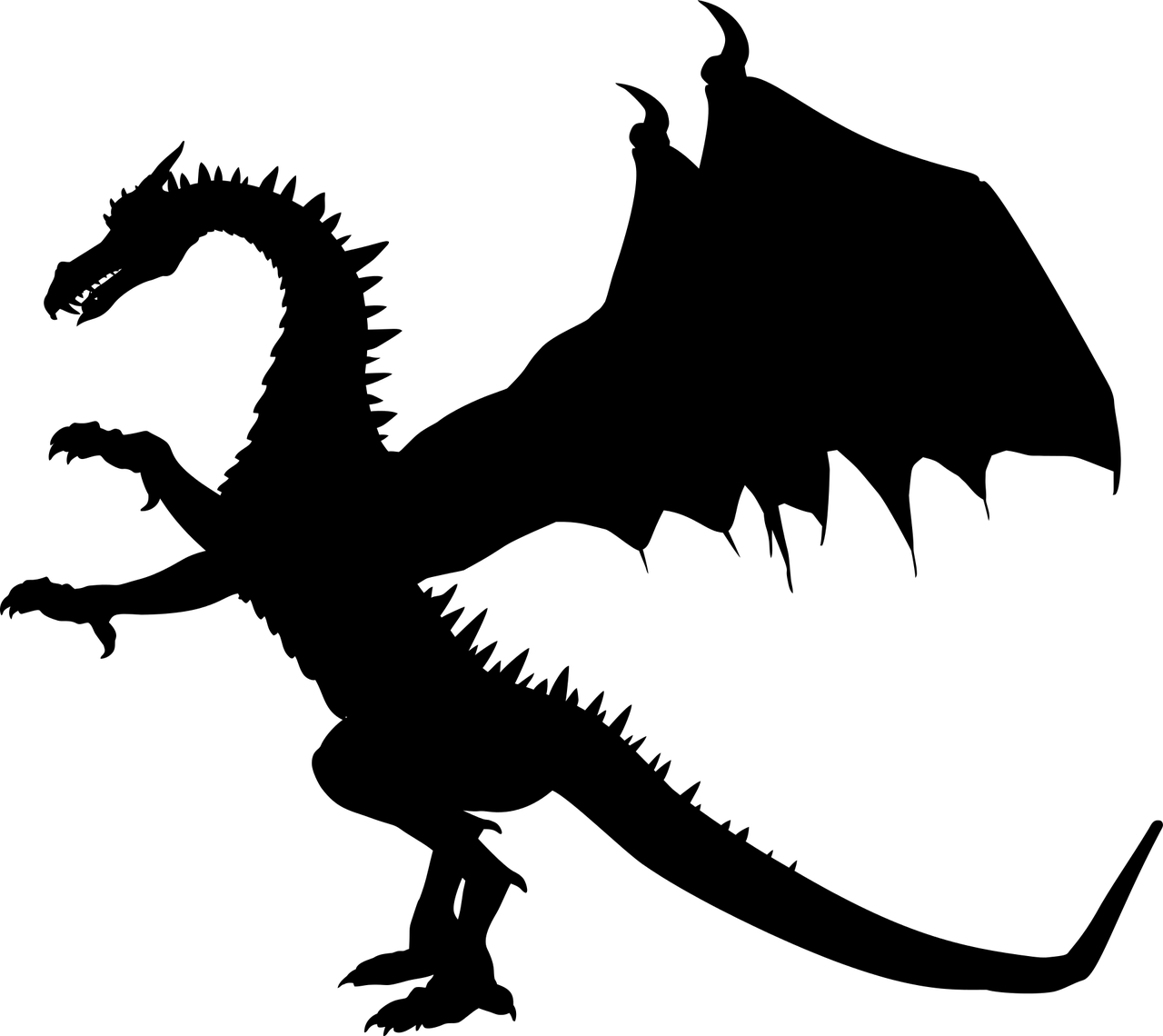
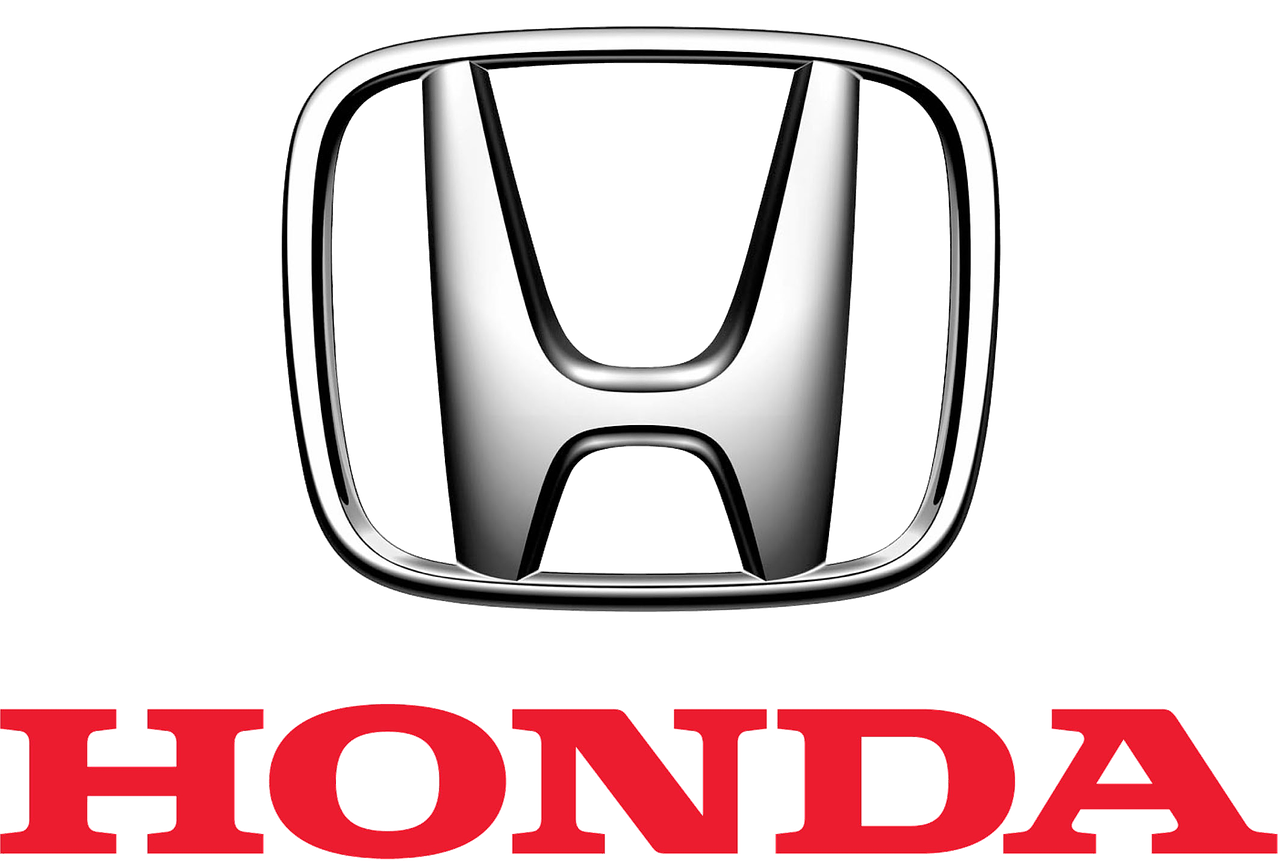










コメントを残す