これまで、「電力供給」についてご紹介してきました。
それでは、私達が電気を需要する設備として私達の身近にある電柱について、どれだけ知っているでしょうか?
今回は、知っているようで知らない「電柱の秘密」についてご紹介します。
→電力供給についてはこちらの記事で紹介しています。
そもそも電柱ってなに?
電柱の役割を考えれば、当然「電線を支えるための柱!」と多くの人が答えるでしょう。
ちなみに、最初は通信のための線を張る目的だったため、この頃から「電信柱」と呼ばれていました。
それでは、今は違うのでしょうか?
電柱に通されている配線は、全て同じだと考えてしまいがちですがそうではありません。
私達は、さまざまな物を利用していませんか?
- インターネット
- ケーブルテレビ
- 電話
など、他にもさまざまな配線があります。
このように、電柱はさまざまな配線を支えています。
さて、とりあえずどれもこれも「電柱」と呼べば間違いがないのですが、実は電柱にかかっている配線によって3つの呼ばれ方があります。
電力柱と電信柱
- 電力柱(でんりょくちゅう)・・・普段、私達の家に電気を送り届けてくれる電線がかかっている。
- 電信柱(でんしんばしら)・・・インターネット・ケーブルテレビ・電話などの通信線がかかっている。
つまり、普段私達がつかう「電信柱」という言葉は、正確には通信線がかかっている電柱のことをさします。
あともう一つ、電線と通信線の両方がかかっている共用柱(きょうようちゅう)があります。
柱を「ちゅう」と呼ばせたり「はしら」と呼ばせたりややこしいですが、困った時は「電柱(でんちゅう)」で。
電柱の見分け方!
ちなみに、電柱は一目で見分けられるようになっています。
例えば、私が住む関西地域では電柱に、関西電力のマークや東西南北を示す「E」「W」「S」「N」の文字が書かれている番号札があれば、関西電力が管理する電力柱。
電柱に、NTT西日本のマークや「L」「R」といったアルファベットが書かれている番号札があればNTT西日本が管理する電信柱
両方の番号札(2枚の番号札)が付いていれば共有柱です。
電信柱の番号札の謎
ちなみに、電柱番号は電柱の住所(所在地)を表わしています。
電柱に、「NTT 新中野支 右1 右4 7」と書かれていた場合、「新中野支線と呼ばれるメイン路線の7本目の電柱から右に行って4本目そこからさらに右に行って1本目の電柱」となります。
このように、基本的に数字は下から呼んでいきます。
そして、「NTTが管理している電信柱」ということが分かります。
さて、台風15号により千葉県では大停電が発生(2019年)しましたが、電柱の倒壊が停電原因の1つとしてあげられています。
それでは、そもそも電柱は簡単に倒壊しまうものなのでしょうか?
電柱の安全性は?
電柱の設置
電柱の長さ
そもそも、電柱の長さを知っていますか?
場所により違いはありますが、約6m~16mの電柱があります。
ですが、少なくとも普段私達が街中で見かける電柱に、16mの電柱なんてないですよね。
実は、「電柱が建てられるときに全身の約6分の1を地中に埋めないといけない」という決まりがあるため、普段私達が目にしている電柱の高さは約5~13mということになります。
2本継ぎコンクリート柱
昔は、電柱に木材(スギ品種の「ボカスギ」)が多く使われていたようですが、ほとんどコンクリートの電柱しか見なくなりました。
とはいえ、木の電柱がなくなったのかといえば現在も地域によっては使われています。

Schratzl / Pixabay
そんな電柱は、基本的にコンクリート製ですよね。
ただ、先程も紹介したように電柱をまともに運ぼうと思えば、約6m~16mもの長さの物を運ぶことになり、コストがかかります。
そもそも、そんな高さの物を設置するには高度な技術が必要でした。
そこで、関西電力では電柱を2分割しフランジを介して10~16本のボルトで接続する構造が採用されています。
このように、電柱1つとっても技術革新が見てとれます。
それでは、そんな電柱にはそもそもどれだけの加重がかかっていると思いますか?
電柱の負担
電柱にかかっている電線は、電柱と電柱の間の重さで1本あたり約50kgになります。
また、一番端っこの電柱にはこの半分ほどの加重が電線によりかかることになります。
つまり、電柱の両側にも電柱があれば同じ力で引っ張られるためバランスがとれます。
ですが、片側にしか電柱がなければ加重が一方にかかり続けるため、傾く可能性があります。
そうならないために、支線を張ってバランスを取るようにしています。
さらに、風が吹けば数百kgの負荷がかかることもあり、そういったことも考慮して作られています。
電柱の耐久性は?
さまざまな工夫がされていることは分かりましたが、「電柱は倒れてこないのか?」という不安はありますよね。
実際、今回の台風だけでなく地震や車が衝突したことで倒れてくることもあります。
それでは、そもそも電柱の耐久性はどうなっているのでしょうか?
電柱の倒壊防止については、経済産業省の「電気設備に関する技術基準を定める省令」に、風速40m/sまで耐えられるように作ることが定められています。
とはいえ、「超過すればすぐに倒壊する」というものでもないようです。
例えば、東京電力管理の電柱ではそもそも2018年までは「暴風」が原因で倒壊した事例はなかったようです。(倒木などにより電柱が倒壊したことはあるが、風の力だけで倒壊したことはない)
ところが、今回の台風15号では多くの電柱が倒壊したという事実があります。
このことから、今回の台風はこれまで暴風でさえ倒壊しなかった電柱が倒壊したことが示唆されています。
最後に
安全性の向上は日々研究されており、例えば「プレストレストコンクリート」と呼ばれる本来コンクリートが弱いはずの引っ張る力に強いという特徴があるコンクリートの開発。
また、普通ならコンクリートはひび割れることで腐食の心配がありますが、そのひび割れを閉じるという特徴まであります。
このように、確かに電柱にはさまざまな技術が使われています。
国土交通省によれば、電柱の本数は毎年約7万本ずつ増加しH28年では3,578万本になっています。
ただ、これまでなかったことが当たり前のように起こるのが昨今の災害です。
今後は、今回の千葉県の大規模停電を機に「無電柱化」の話しが進められていくかもしれませんね。
参考
関西電力:教えて!関電
→https://www.kepco.co.jp/brand/for_kids/teach/
国土交通省
→https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_03.html
ウェザーニュース:電柱は風速何メートルまで耐えられる?
→https://weathernews.jp/s/topics/201804/130205/








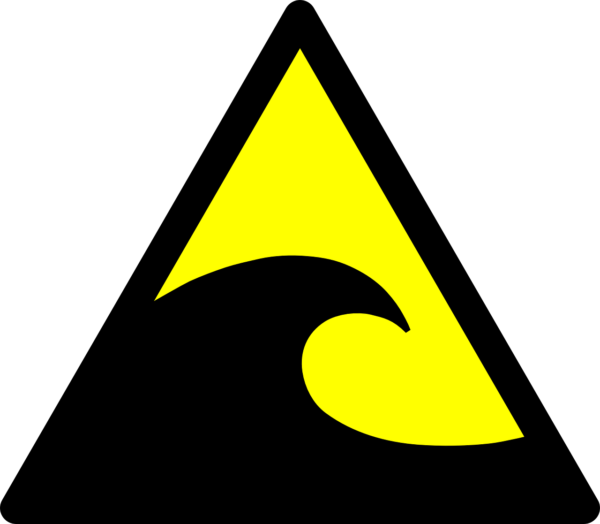











コメントを残す