この記事では、「混雑率と指標の変化?」についてお伝えしています。

多くの人が、満員電車を経験しているのではないでしょうか?
学生・社会人・旅行者などなど、電車に乗る理由は人それぞれだと思います。
ところで、そんなときに気になる「混雑率」という言葉がありますよね。
しかも、この「混雑率」は当たり前のように100%を越えていきますよね・・・
普通に考えれば混雑率が100%で満員の状態と考えるかもしれませんが、実はそうではありません。
今回は、「混雑率は200%を越える!?」についてご紹介します。
そもそも「混雑率」はどうやって決めているの?
先に答えを言ってしまうと、この「混雑率」はそれぞれの鉄道会社が計算して発表した数字です。
それでは、どうやって計算しているのでしょうか?
日本民営鉄道協会によれば、「輸送人員÷輸送力」で算出される混雑度の指標のことを「混雑率」と呼んでいます。
ちなみに、通勤車両での「混雑率100%」は座席が全て埋まり、吊革がだいたい使用されドアの前に人が数人立っている状態とされています。
つまり、座席の数だけではなく吊革まで含めた通常の輸送力が「分母」ということになります。
それでは、混雑率について詳しく見ていきましょう。
「混雑率」ってなに?
国土交通省によれば、「混雑率」は以下のように定義されています。
- 100%:乗車定員(座席に着くか、吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる)
- 150%:広げて楽に新聞を読むことができる
- 180%:折りたたむなど無理をすれば新聞を読める
- 200%:身体がふれあい相当圧迫感があるが、週刊誌程度なら何とか読める
- 250%:電車が揺れるたびに体が斜めになって身動きができず、手も動かせない
私が満員電車のイメージは、まさに250%の身動きがとれない状態でした。
あなたがイメージした満員電車は混雑率◯%だったでしょうか?

それにしても、「新聞」や「雑誌」が混雑率の基準になっていたとは驚きだったのではないでしょうか?
ただ、新聞や雑誌を読んでいる人よりも、実際はスマホを見ている人の方が圧倒的に多いですよね。
そもそも、スマホがあれば「新聞」も「雑誌」も読めてしまいます。
最近では、オーディオブックなど聞くことができるアプリも登場しています。
つまり、「新聞」や「雑誌」を直接手に取って読む必要がなくなりました。
国土交通省が、混雑率を「新聞」から「スマホ」へ?
実は、国土交通省は令和3年1月25日に「鉄道利用者アンケート調査結果」が発表されました。
その中で、従来の「新聞が読めるかどうか」に代えて「スマホの操作のしやすさ」を公的な資料に初めて取り入れられました。
もちろん、「アンケート」ですのでまだ白書などに取り入れられるかどうかまでは分かりませんが、少なくとも国の資料に記載されることになりました。
アンケートでは混雑率が9段階に!?
- 40%:詰めれば全員が座れる程度だが、数人が立っている。あるいはそれ以下。
- 60%:座席が埋まり、座席前に座席数の半分程度の人が立っている。各ドアの前には1~2人が立っている。
- 80%:座席が埋まり、座席前に座席数と同人数程度の人が立っている。各ドアの前には2~3人が立っている。
- 100%:座席が埋まり、座席前に座席数と同人数程度の人が立っている。各ドアの前には6~7人が立っている。
- 120%:座席が埋まり、座席前に座席数と同人数程度の人が立っている。各ドアの前は空間が埋まっているが、車両の中程はまだ余裕がある。
- 150%:車内の空間が埋まり、肩が触れあわない程度で人が立っている。スマホなどの操作は楽にできる。
- 180%:車内全体で肩が触れあい、スマホなどの操作がしにくくなる。
- 200%:体が触れ合い圧迫感があり、車内の中程に進むことができない。スマホなどの操作は何とかできるが、長い操作は難しい。
- 250%:車内全体で身動きが取れず、押し込まなければドアが閉まらない。
このように、説明されています。

新聞とスマホの混雑率の違いは?
新聞の混雑率・・・
- 150%:拡げて楽に読める
- 180%:無理をすれば読める
- 200%:週刊誌なら読める
⇩ ⇩
スマホの混雑率・・・
- 150%:楽に操作できる
- 180%:操作がしにくい
- 200%:操作は何とかできるが、長い操作は難しい
このように、混雑率の目安が「新聞・雑誌」から「スマホ」へ変更されています。
*単純に、200%で週刊誌が読めるなら、スマホは週刊誌よりも楽に扱えそうですがそれはそれとして・・・
今後は、新聞ではなくスマホで混雑率が示されるようになるかもしれませんね。
最後に
今では、スマホがあればたいていのことができるようになりました。
そのため、電車の混雑率だけでなく多くの指標が変わっていくでしょう。
例えば、以前紹介した「おかしな校則」では下駄の禁止なんてものがありましたが、時代に即していないですよね・・・
さて、ほとんどの人が利用していないものを指標にしても意味がありませんよね。
今後も多くのことが変わっていくことが予想されますが、整備されるまではまだまだ時間がかかるでしょう。
参考
犬耳書店:電車の混雑率は、どうやって計算しているの?
→https://inumimi.papy.co.jp/inmm/sc/kiji/1-1007254-84/
レスポンス:列車の混雑率「新聞」から「スマホ」表現に変更…国交省が試行[新聞ウォッチ]
→https://response.jp/article/2021/05/18/345892.html
一般社団法人 日本民営鉄道協会:混雑率
→https://www.mintetsu.or.jp/knowledge/term/16370.html


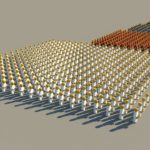

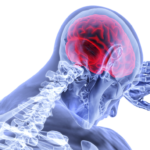



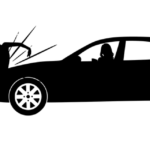




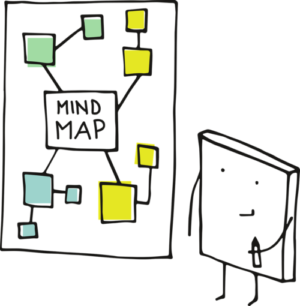
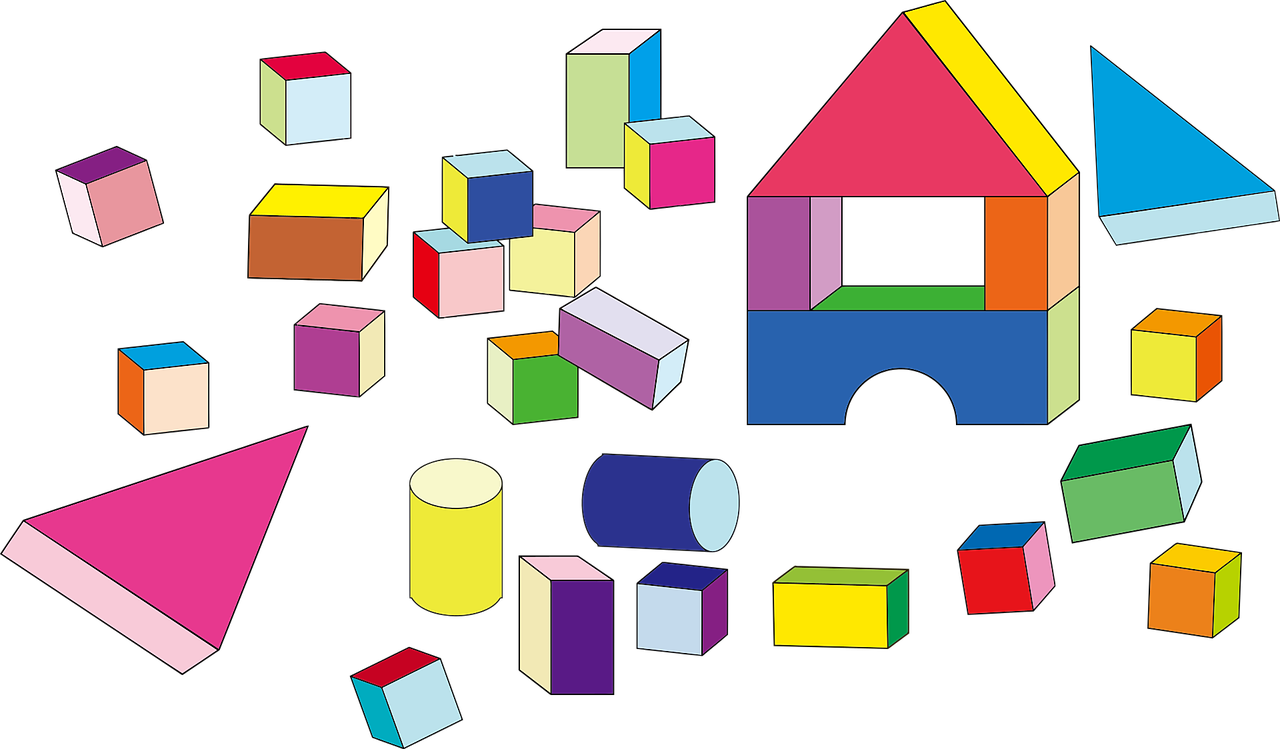






コメントを残す