18歳から成人?
子どもの成人年齢が18歳に変わることはみなさんニュースで聞いたことがあるかと思います。
今回は、18歳で成人となったときに注意すべき「契約」について紹介します。
2018年時点で20歳が成人年齢ですが、2022年4月1日からは18歳から成人ということになります。
親としては、心配になりませんか?
なぜなら、高校を卒業したら大人ということになるのですから。
18歳から個人の責任で契約ができる
高校を卒業したら、個人の責任で契約をしてもいいことになります。つまり、保護者の権利である「未成年者取消権」が行使できなくなります。
未成年者取消権
契約者が、契約時に20歳未満で法定代理人(親権を有する物なので親がほとんど)が同意していない場合は契約じたいをなかったことにできます。

stevepb / Pixabay
ただし・・・
①契約時に年齢などを偽っていない。
②婚姻経験がない。(16歳でも結婚すれば成人とみなされます)
③法定代理人から許可された財産(小遣い)の範囲を超えていること。
④取消権が時効になっていない。
- 未成年者が青年になった時から5年間→18歳で個人でいつの間にか契約していたら23歳(順調に進学していれば大学卒業と同時)で取り消せなくなります。
- 契約から20年間
など、全てが当てはまって初めて行使できるものが未成年者取消権になります。
*未成年者取消権が行使できれば、代金の支払い義務はなく支払った分もかえってきます。つまり、最初に伝えたように、契約じたいがなかったことになります。
契約と18歳
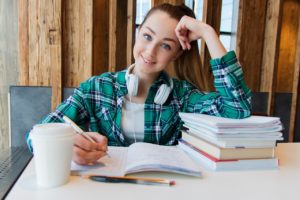
nastya_gepp / Pixabay
これが、高校生が卒業したら大人として認められるという内容の一部です。考えてみてください、高校生の時点では本業は勉強ですよね?
アルバイトをしたことはあっても実際に働いているとすれば、中学校を卒業して働いている子ども達だけでしょう。
高校生ではアルバイトをしている学生も多いですが、自立しているわけではありませんよね。つまり、社会に出た経験がない子どもに突然「責任もって契約してね!」という権利?
が付与されることになります。
大学に行くと一人暮らしが始まる学生が増えます。つまり、行動範囲が広がる・交友関係が広がるなどこれまでと生活が大きく変わります。
もちろん、一人暮らしに限ったことではありません。ですが、一人暮らしの場合子どもは自分でなんとかしようと親にも相談しない可能性があります。
その場合、さらに取り返しのつかない状態になってからしか親は気づくことしかできない可能性があります。
インターネットで、いつでもどこでも契約ができてしまう現在。受験勉強と並行して教えるのは難しいと思いますが、どんなに遅くても高校生になったら「契約」について教える必要があるでしょう。

3dman_eu / Pixabay
*就職支援活動サービスをおこなっているハタラクティブより、中卒者の就職率は、0.5%未満。
*文部科学省の「平成29年3月高等学校卒業者の就職状況(平成29年3月末現在)に関する調査」では、高校生の就職率は約17.5%。
つまり、8割以上の18歳は社会に出ないことが分かります。
契約とは?
法律的な責任が生じる約束のことを契約といいます。単純な口約束でも成立します。
契約が成立すれば、
- 売主は、買主に商品を引き渡す義務
- 買主は、売主に代金に支払う義務が発生します。
この義務に従わなかった場合
- 義務に従うことを求める
- 損害賠償を求める
- 契約を解除する
となります。当然ですよね。お金を払ったのに商品がない。逆に、商品を渡したのにお金が支払わなければ契約が成立していないのですから。
このように、契約は怖いものではなく普段の生活でなくてはならないものです。
なにが問題になるのでしょうか?
ここでは、印鑑を例にして説明したいと思います。
契約といえば印鑑が必要になりますよね?
それでは、「捨印」はなんで押すか知っていますか?
契約書や申込書に捨印と書かれていて「ここに押してください」と言われて押したことがある人もいるのではいでしょうか?実はこの捨印、書類にミスがあった場合、売り手側が買い手の意思に関係なく、ある程度までなら書類を書き換えてもいいというハンコになります。つまり、誤字が見つかった時に「訂正印」を本人ではなく書類作成者(売り手)が押せるということです。
ここで、「捨印は危険だ!」と思ったのなら契約についてもう一度勉強する必要があります。
それは、捨印は万能ではないということです。それはそうですよね?
あなたの捨印が書類に押されているからといって、商品の金額やそもそも商品じたいを書き換えられては契約もなにもあったものではありません。あくまで、住所などの誤記を訂正するために使われるものです。
もし、捨印がなければご表記が見つかったさい再度契約書をあなた自身が書き直すまで契約はストップしてしまいます。その時間的なロスをなくすために使われるのが捨印です。
契約のさいに最も大事なことは、
- 契約書のコピーを作成が完了した時点でもらうこと。(普通は渡されます)
- 銀行印や実印に市販のハンコを使わないこと。
この2点は最低限知っておかなければなりません。
ないとは思いますが、100円均一といった既製品を銀行印や実印に使
っていないですよね?

TayebMEZAHDIA / Pixabay
隣の人がもっているハンコと同じならハンコの意味がありません。
指紋がみんな同じだと思えば分かりやすいかもしれませんね。みんながおなじ指紋なら指紋認証の意味がないですよね。
このように、捨印一つ例に上げても説明することはたくさんあります。ですが、知らないではすまされないポイントです。
あなたは契約について親から教えてもらいましたか?
私の場合は、大学生のときに「ハンコは簡単に押すな!」とだけ教えられました。ですが、生活していると意外とハンコを押すタイミングはありますよね?
これだけのアドバイスではよく分かりません。
そうです、大人といってもそもそも契約について知らない大人が私も含めて大勢います。だから、子どもにもしっかり説明することが難しいのではないでしょうか。
2022年4月から18歳でおこなえる契約にはどんなものがある?
法務省民法改正Q&Aによれば、

TheDigitalWay / Pixabay
- 携帯電話の購入。
- クレジットカードの作成
- ローンを組んで自動車を購入
といった本格的な契約が個人(18歳)でできるようになります。
他にも、10年有効のパスポート取得や居住地を自分で決めるなど様々なことが法律的に可能になります。
*さらに、女性の婚姻が16歳→18歳に引き上げられます。
例えば、結婚は両性の同意のみで法律的にはできます。ですが、現実には親の同意が重要ですよね。
このまま絵に書いた餅になればいいのですが、確実に18歳を狙った契約詐欺が発生することは目に見えています。新しい制度ができるまで無法状態になるのがいつものパターン。脱法ハーブが注目されたときもそうでしたが、どれだけ多くの被害が出るかは予想もつきません。
まとめ
自己責任時代に押しつぶされないように自分の身は自分で守れるようにするしかありません。
これまでは、18歳から大学に通っているとするなら少なくとも2年間は猶予期間があると考えることができましたが、これからは違います。全ての子どもが18歳になれば、成人とみなされることになります。
実家で、昨日まで毎朝お母さんに起こされていた・ご飯を準備されていた・塾に通わしていたそんなあなたのお子さんが、高校卒業と同時に成人したということで様々な契約が一人でできてしまいます。
詐欺師にとっては大きなカモになってしまうでしょう。もし、「ブログ」や最近はやりの「ユーチューバー」で生計を立てようと考えているなら勉強しようとするかもしれません。もちろん、そのための情報商材が数多くあります。ですが、働いた経験もなく突然そんなものに手を出すようなことがあれば失敗することは目に見えています。
そして、詐欺にあいクレジットカードで借金をする。分割にできるからと安易にリボ払いにするなど深く考えすにおこなう可能性も考えられます。
親の言葉をどれだけ聞いてくれるかもわかりません。日々の生活の中で暮らしの一部として早めに伝えていくしかないでしょう。
どちらにしても、結局は責任を取るのは親(あなた)ということになると予想されます。難しいことはわからないと言っている場合ではありません。あなたも私も子どもに教えられるように契約の危険性と必要性について勉強しないといけない時代がもうそこまできています。
参考
東京クラブweb
→https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
法務省民法改正Q&A
→http://www.moj.go.jp/content/001261887.pdf
文部科学省「平成29年3月高等学校卒業者の就職状況(平成29年3月末現在)に関する調査について」→http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/19/1385931_001.pdf
ハタラクティブ
→https://hataractive.jp/chusotsu/jobhunting/62/
PRESIDENT ONLINE
→https://president.jp/articles/-/3031?page=2


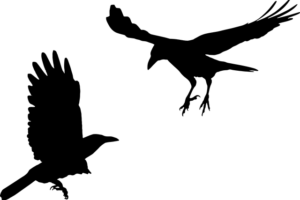







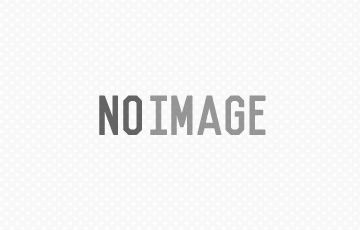



コメントを残す