以前、AEDについてご紹介しました。
AEDは、「心室細動」という心室が細かく震えるだけで収縮することができない(心停止)状態。つまり、血液を送り出せない危険な状態になっている人に対して使用されます。
さて、今回はそんな「AEDの効果について、世界で初めて明らかにされた研究成果」についてご紹介します。
→AEDについては、こちらの記事で紹介しています。
AEDの役割とは?
AEDについて振り返ってみよう!
そもそも、心室細動を引き起こした人は、数秒で意識がなくなります。そして、約5分もすれば脳に取り返しの付かない障害を残してしまいます。
そうなれば、まもなく死にいたるため、治療は1分1秒を争います。
そこで、誰もが手順通りに操作することで使用できる「AED」を使うことで、電気ショックを心臓に与えて心臓の機能を正常に戻します。
これが、AEDの役割です。
→AEDとは、心室細動(心臓の痙攣)を引き起こした心臓に電気ショックを与えることで、心臓を正常な機能に戻すための医療機器。(乳児にも使えるため、全年齢が対象)
国立循環器病研究センターなどがまとめた世界初の研究成果!?
今回の研究成果は、AEDを使用した「その後の話」です。
つまり、「AEDを利用したかどうかで予後が大きく変わる!?」ことを世界で初めて明らかにしました。
~具体的になにがわかったの?~
結論からいえば、私達(市民)の誰かがAEDを使って心室細動を引き起こした人の心肺蘇生をしたとします。
仮に、この救護した時点で自己心拍が再開しなかったとしても、その後の神経学的復帰(脳障害による後遺症)を改善させる可能性をあきらかにしました。
~社会復帰の可能性を引き上げることがなぜそんなに重要なの?~
そもそも、心室細動は日本で年間約110,000件もあります。
さらに、蘇生科学が発達した現代でさえ、命が助かったとしても社会復帰率は約7%前後しかありません。
つまり、年間の発症人数110,000人中、約7,700人しか社会復帰ができていません。逆に言えば、年間10万人以上が社会復帰できない状態に陥っていることを意味しています。
このことから、社会復帰の可能性を底上げすることがいかに重要なことか分かるのではないでしょうか?
それでは、研究成果について見ていきましょう。
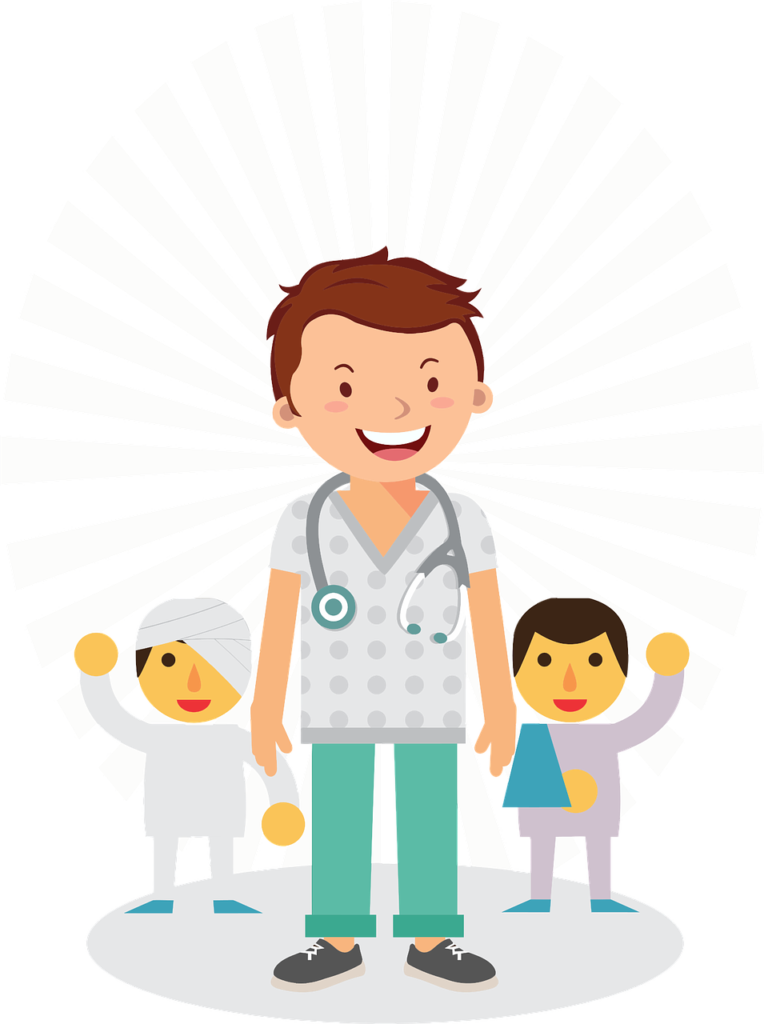
OpenClipart-Vectors / Pixabay
研究成果とは!?
2005年~2015年までの間に日本で1,299,784例の院外心停止が発生しました。
その内、市民による目撃があり心肺蘇生(CPR:CardioPulmonary Resuscitation)が施工された心室細動により心停止した患者さん28,019例のうち、さらに最終的に救急現場到着時点で心停止が持続していた患者27,329人が分析されました。(「確実に、心肺蘇生が続けられていた症例のみが抽出された」ということ)
つまり、「救急隊員が現場に到着するまで市民が心肺蘇生を試みていたが、心停止が続いていた症例」に絞って研究されたということです。
どんな研究をしたの?
先程、紹介した27,329人の症例のなかで、「AEDと心肺蘇生(CPR)を併用」と「AEDを使わない従来の心肺蘇生(CPR)のみ」とが解析されました。
症例数としては、このようになりました。
- AED+CRP:2,242症例
- CRP単独 :25,087症例
この時点で、「CRPのみ」が「AEDと併用」よりも、10倍以上も多いことが分かります・・・
AEDの利用率は「20人に1人」ともいわれ、また別の問題があります。
さて、今回の研究から生存率が大きく変わることが分かりました!
生存率と社会復帰に大きな違いが!?
~30日時点での生存率~
- CPR+AED併用:44%
- CPR単独 :32%
→併用した方が、12%向上する。
~30日時点での神経学的転帰良好率(後遺症の改善率)~
- CPR+AED併用:38%
- CPR単独 :23%
→併用した方が15%向上する。

OpenClipart-Vectors / Pixabay
つまり、AEDを併用した方が「生存率」・「その後の予後」のどちらも、10%以上高くなることが分かりました。
生存率はもちろん、これまで社会復帰が難しくどうにもできない状態から、10%以上も引き上げられたことは大きな成果だと言えます。
*世界医学雑誌ランキング総合医学部門トップクラス(2018年journal impact factor 59.102)であるThe LANCET誌に2019年12月18日付で掲載されたほどです。
AEDは自動音声で使い方を教えてくれます。
そして、救護には複数人で当たる必要があります。
今回の記事は、「もしもの時は、AEDを使うことで生存率を上げ、その後の予後を良い状態にしてくれるため、できる限り使いましょう!」ということが、科学的に証明された研究成果のご紹介でした。
最後に
AEDは駅や施設などさまざまなところで目にするようになりました。
ただ、使用率がまだまだ少ないことが指摘されています。つまり、多くの場所で環境は整っているのに、使えていない状態です。
- 心肺蘇生を実施する人
- 救急車を呼ぶ人
- AEDを持ってくる人
救護の際は、それぞれ役割が必要になります。一人で救命措置をすることは難しいため、近くの人に協力を仰ぐ必要があります。
もしもの時のAEDを使う・使われるのは、今日かもしれません。
知識の1つとして、AEDの効果についてぜひ覚えておいて下さいね。
参考
国立循環器研究センター:世界初!市民によるAED(自動体外式除細動器)を用いた心肺蘇生が除細動不成功であったとしても、その後の脳障害を改善させる可能性について
→http://www.ncvc.go.jp/pr/release/aed.html














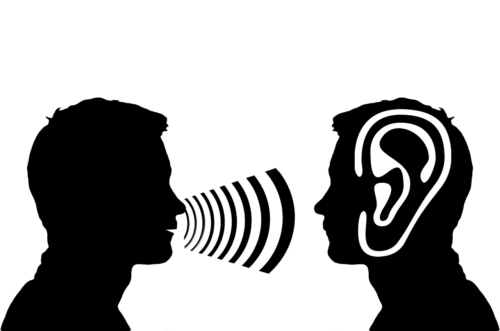






コメントを残す