「校則」について、これまで紹介してきましたが同時に「校則で生徒を規制してもいい!」という法律がないことも紹介しました。
ですが、例えばいまだに「下着の色が校則で定めた色(白色)と違う」と女生徒が男性教師から注意を受ける。
他にも、2019年5月現在も裁判中ですが、地毛が茶髪の高校3年生の女子生徒の髪の毛を「脱色・染色の禁止」という校則を理由に黒く染め、地肌や髪がボロボロになり染められなくなるとその女子生徒を学校から追い出した学校。(女子生徒の授業の出席禁止・修学旅行の禁止・机をなくす・出席簿から削除→女子生徒は不登校に・・・)
学校側は、「校則」にそう書かれているため校則通りに実施しただけと主張し真っ向から対立しています。
校則に関する訴訟は、こちらの記事でも紹介しています。
生徒側が学校に訴訟を起こしても裁判ではほとんど勝てないため、「校則は法律や憲法よりも強い?」と錯覚してしまいますが、本来は「法律」や日本の最高法規である「憲法」が優先です。
「なぜ、校則がこんなに優遇されるのか?」調べてみました。
校則の位置付けは?
校則の規定は法律ではありませんが、様々な考え方があります。
特別権力関係論
これは、「法律の根拠がなくても、人権が制限でき司法審査も排除される」という考え方です。
→現在では批判が多く、必要性じたいが問題視され人権規定が原則として適用されます。
ということで、こちらはあまり気にしなくてもいいでしょう。
存在契約論
主に、高等教育や私立学校について校則の存在や学校の制定権について、「入学時に自由意志に基づいて契約が成立したもの」と考える説。
弁護士ドットコムでこんな相談を見つけました。
→「頭髪規制がない高校に入学したのに合格後に校長が変わり、頭髪規制がおこなわれた。」という事例。
入学前に、学校側には頭髪規制がないことを確認し学校側も「さすがに、いきすぎの場合は注意はする」と言質も取っていたようです。
「頭髪規制がないことを売り」にして生徒を集めていたのに、校長が替わり結局、入学当初から頭髪規制が厳しくなったというもの事例。
→弁護士の回答は、「判例からみて学校の違法性はみられない。」ということです。つまり、「入学時に自由意志で決定した高校の校則が変わっても問題ない」ということなので、この理論も当てはまらないでしょう。
そもそも、義務教育にはほとんど選択権がありませんが・・・
部分社会論
「学校は自立的な部分社会であるため、そこでの内部規律については法や人権が犯されない限り外部は干渉すべきではない」とされるもの。
→現在、もっとも主張される理論です。
しかし、例えば校則を理由に「茶髪などの地毛を黒く染めさせる」ということが実施されています。そもそも憲法で身体的特徴を否定することは禁止されています。
このように、この理論も当てはまらない校則が存在していますが現実的に実行されています。
「校則」についてはこちらの記事で紹介しています。
文部科学省の通達
校則とは,児童生徒が健全な学校生活を営み,より良く成長・発達していくため,各学校の責任と判断の下にそれぞれ定められる一定の決まりです。校則自体は教育的に意義のあるものですが,その内容・運用は,児童生徒の実態,保護者の考え方,地域の実情,時代の進展などを踏まえたものとなるよう,積極的に見直しを行うことが大切です。
文部科学省では,平成9年度に実施した「日常の生徒指導の在り方に関する調査研究」の調査結果を受けて,10年9月に,各学校における校則と校則指導が適切なものとなるよう都道府県などに対し通知を出し,指導の徹底に努めています。
とあります。
校則は、学校の責任と判断で決まる。ただし、「積極的に見直しをおこなうことが大切」と明記されています。
そして、「生徒や保護者・地域・時代によって変わる」ともあります。
ですが、現実にはおかしな校則がまかり通っているためこの通達も当てはまりません。
その他
「子どもの権利条約」もありますが少なくとも、校則に関しては機能していないようです。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
→18歳未満の全ての児童が対象です。
第2条 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
とあり、児童の権利(人権)が保証されています。
*日本では、1994年5月22日から効力が発生しています。
裁判の判例が根拠?
これまで、校則にめぐっての裁判で生徒側が勝訴した事例が本当に少ないです。基本的には、学校側が勝つことが多いようです。
生徒側が勝訴した事例
修徳高校バイク事件(東京高判:平成4年)
「校則で禁止されていたバイクに、無届けで運転免許を取得し乗車した」ことを理由に退学処分を受けた男子生徒側が訴訟を起こした判例。
→校長権限で退学処分にすることはできますが、その対象は改善の見込みがない生徒です。ですが、この男子生徒は素直に学校の指示にも応じバイクの兼以外は特に問題もない生徒でした。
そのため、裁判所は学校の退学処分は違法な行為と判決し確定されました。
ちなみに、上記の裁判で「日本国憲法第13条 幸福追求権」が主張されましたが、私人間における憲法の効力は否定されています。
幸福追求権の根拠
*上記の裁判で、「幸福追求権は、国・公共団体などと個人との関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律するものではない」とされ、私立学校を国や公共団体と同一視できないとされました。
→つまり、私立学校は公権力ではない。だから幸福追求権は関係ない(当てはまらない)ようです。
生徒側の敗訴判例が多いのは、こういった事情もあるのかもしれません。
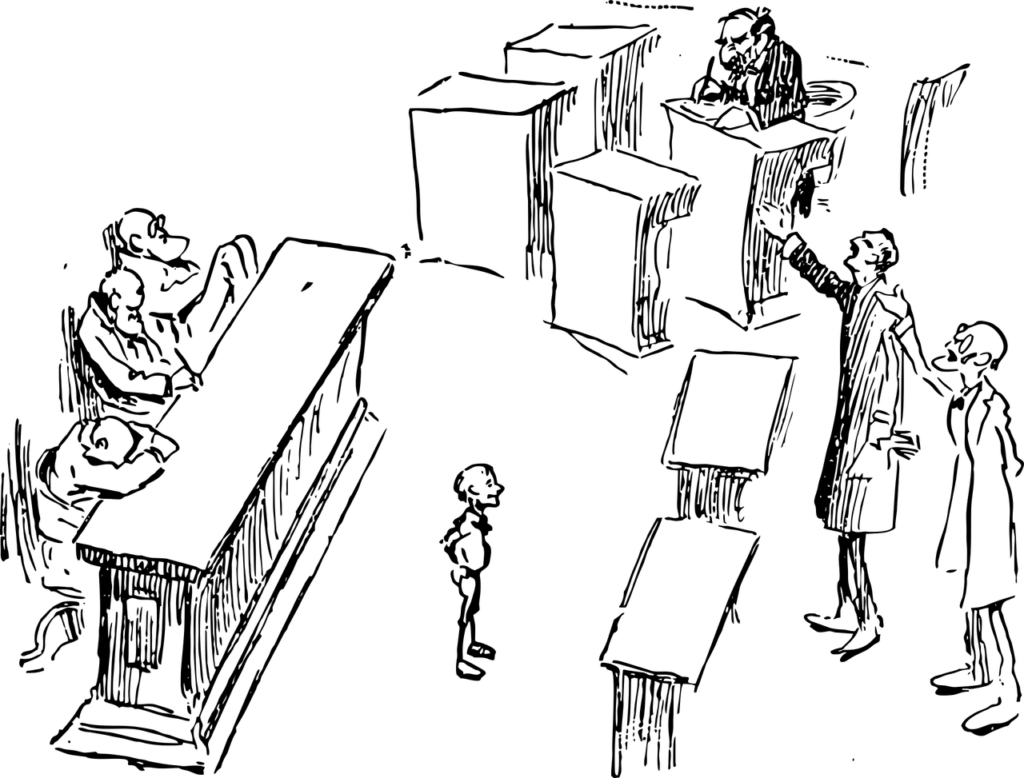
b0red / Pixabay
最後に
校則について調べてみましたが、「法的根拠がないものを守るためにみんな必死?」という印象がかなり強くありました。
もちろん、校則は必要ですが「合理性もなにもない、誰もなぜ正しいか説明ができない校則に意味があるのか?」と正直感じてしまうほどでした。
子どもをもつ親としては、「自分たちが子どもの頃に受けていた教育(校則)をそのまま盲目的に受けさせていいのか?」という漠然とした不安があります。
例えば、「社会は不合理に従わないといけないから、その練習」なんていわれます。私も言われたことがあります。
その結果が今の働き方なわけですが・・・
つまり、誰もが(今の働き方に上司に文句も疑問も伝えず)不満を我慢しながら、言われたことをする社会。おかしなことも受け入れて、違法性を調べもしない社会・・・
経営者にとっては、これほど都合のいい社員はいないでしょう。
確かに、子どもは大人の鏡ですね。
「常識の範囲」で決まるのが校則ですが、その常識は「いつできて」・「誰」の常識かが問題になっています。
参考
弁護士ドットコム
→https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_249253/
文部科学省
→http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/002/002/0205.htm
児童の権利に関する条約
→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
我が国における校則訴訟と子どもの人権
→http://www.tezukayama-u.ac.jp/tlr/oshima/oshima4_j.htm
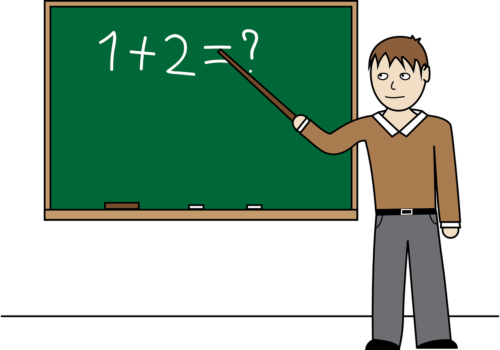



















コメントを残す