●この記事では、新型コロナ相談窓口に連絡することから始まる診察についてお伝えしています。
新型コロナウイルスの影響により、体調不良になってもこれまでのように病院受診ができなくなりました。
というのも、そもそも新型コロナウイルスは無症状であっても感染が疑われるためです。つまり、症状に関係なく感染している可能性があるため、病院側としては全ての人を疑うことになります。
そのため、私達はもしも風邪症状のために医療機関を受診しようと思えば、「新型コロナ相談窓口」に電話相談する必要があります。
→各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先はこちら。
今回は、「新型コロナ相談窓口に相談した後はどうしたらいいの?」について紹介します。
*「公益財団法人 宮城県結核予防会」を例に、続けられてきたコロナ対応についてお伝えしています。
→自治体によって対応が変わるため、受診する前にまずは自治体のホームページの確認をお願いします。
医療機関への受診方法がこれまでと全く違う!?
基本的に、「体調不良になった!」としても、いきなり医療機関へ受診してはいけません。
まずは、冒頭で紹介した各都道府県の新型コロナウイルス相談窓口に電話相談することから始まります。
この電話相談により、担当者から「症状の経過」や「持病の有無」などが詳細に聞かれることになります。
→電話相談の結果、担当者が受診の有無を判断されることになります。
受診が必要と判断された場合は・・・
- 指定専門病院
- かかりつけ医療機関
このどちらかが判断されます。
それでは、受診が決まった場合、直接医療機関へ行けばいいのでしょうか?
受診が決まっても事前連絡が必須!
実は、医療機関の種類に関係なく、事前に必ず電話連絡をして相談しなくてはいけません。
→直接受信すると感染拡大のリスクにつながるため。
つまり、私達が「医療機関へ受診しよう」と思えば・・・
- 相談窓口に連絡して担当者に医療機関の指示を受ける
- 指示された医療機関へ連絡してから受診
このように、受診までに2回連絡しなくてはいけません。
当然、受診時にはくしゃみや咳がなくてもマスクの着用が必須となります。
受診が決まったら?
相談窓口の担当者から受診の必要性が認められ、医療機関が指定。指定された医療機関に連絡して、ようやく受診できるようになっても注意事項があります。
例えば、特に小児の患者さんの場合は診察時に嘔吐する可能性があるため、ジュースや食べ物をあまり与えないようにする必要があります。
また、風邪症状の患者さんは「電話対応」や「隔離しての対応や診察」となるため、隔離する準備ができるまで車などで待機する場合もあります。
ただし、症状がでてすぐに受診しても意味がありません。

症状が出てすぐは区別が付かない!?
実は、普通の風邪も新型コロナウイルスも症状が出てからの最初の数日(1~4日)は、区別が付きません。
つまり、インフルエンザも含めて病気の診断ができない状態です。
そもそも、通常の診療所や病院では新型コロナウイルスの検査はできません。仮に早く診断できても肺炎やそれの重症化を防ぐ方法もありません。
ちなみに、PCR検査の感度は70%程度しかないため、「症状・問診・PCR検査(陰性)」を確認したとしても「新型コロナウイルスではない!」という診断書は出せません。
これが、いわゆる「偽陰性」の可能性です。(本当は陽性だが、検査結果により陰性が出てしまう)
ちなみに、インフルエンザの感度はさらに低く、症状が出現して24~48時間経過した時の最大感度でも、60%程度しかありません。
→「偽陽性と偽陰性」については、こちらの記事で紹介しています。
このように、「検査すれば診断できる!」と考えている人も多いかと思いますが、残念ながら万能な検査はありません。
どこまでいっても、「偽陽性」や「偽陰性」の問題がつきまとうことになります。
最後に
今回は、実際の医療機関「公益財団法人 宮城県結核予防会」によるコロナ禍における風邪症状時の受診時の注意点についてお伝えしました。
この資料が作られたときは、まだマスクが品薄でなかなか手に入らない時に作られた資料です。
今では、2021年2月の上旬から新型コロナウイルスワクチンの接種が開始されることになっています。
とはいえ、コロナ対策は緊急事態宣言が再度発表されるなど、今も対策が続けられています。
次回は、そもそも受診の必要がない「オンライン診療」についてお伝えします。














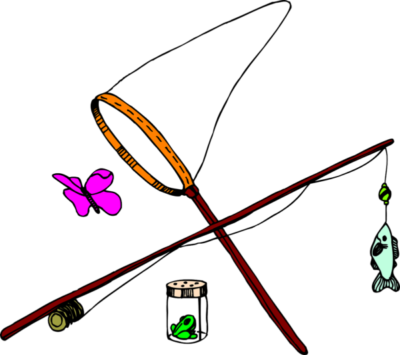






コメントを残す