●この記事では、総合表示の義務化についてお伝えしています。
軽減税率が導入されたことで、さらにややこしくなってしまった消費税。
そんな消費税の表示が、2021年4月から新しく変わることをご存じでしょうか?
今回は、「消費税の総額表示」についてご紹介します。
そもそも「消費税」ってなに?
そもそも消費税は、1989年(平成元年)4月に消費税法が施行されたことから始まりました。
さて、そんな消費税は、消費一般に広く公平に課税される「間接税」です。
「間接税」ってなに?
間接税というのは、「納税者:のうぜいしゃ(税金を納める義務がある人)」と「担税者:たんぜいしゃ(税金を負担する人)」が、異なる税金のことを言います。
確かに、私達は納税者であり日頃から「8%・10%」と消費税を支払っていますよね。
ですが、実は私達が直接納税しているわけではありません。
どういうことかと言えば、例えば100円均一に行って消費税10%の商品を購入すれば、商品の価格に10%を足してレジで支払っていますよね。
つまり、100円の商品なら、110円を支払わないと購入できませんよね。
確かに、私達消費者は消費税を支払っていますが、納税しているわけではありません。
→実際に消費税を納税しているのは「お店側」。

例えば、私の場合は個人事業主ですので税務署に行って確定申告をすることになります。ですが、私が1年間で購入した全ての商品にかかった消費税を、個人で納めに行くようなことはありません。
もしも、「購入した商品の消費税を個人で納税しないといけない!」なんてことになれば、自分が買った商品のレシート1年分を保管した上で、書類を作成し納税に行かなくてはいけなくなるでしょう。
そうなれば、毎年大勢の人が税務署に押し寄せることになります。
そうならないために、「私達納税者の代わりに、お店などが担税者として間接的に納税してくれている」ということになります。
そのため、消費税は「間接税」と呼ばれます。
*ちなみに、「タバコ税」や「酒税」など、特定の物品やサービスに課税されるのは「個別消費税」と呼ばれる。
消費税の変遷
さて、そんな消費税は1989年に3%から始まりましたがその後・・・
- 1997年4月:5%
- 2014年8月:8%
- 2019年10月:10%(軽減税率導入)
となりました。
→軽減税率については、こちらの記事で紹介しています。
このように、消費税はどんどん変化していきましたが2021年4月1日からは、税込み価格表示が義務化されることになります。
税込み表示価格が義務化?
そもそも、軽減税率が適用されたことで「8%?10%?」と分かりにくくなってしまいました・・・
飲食店いたっては、「テイクアウトなら8%」・「店内なら10%」と、同じメニューでも合計金額が変わってしまいますよね・・・
そんなややこしい消費税ですが、これからは「総額表示」となります。
とはいえ、そもそも価格表示は、『「消費税込」にしなければならない』と消費税法で定められています。
消費税法第63条(価格の表示)
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
とはいえ、これまで総額表示になっていない商品もあったのではないでしょうか?
特別措置が終了する!
そもそも、これまで「税抜価格」など、総額表示なしにできていたのは「消費税転嫁対策特別措置法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)」があったためです。
この法律は、2013年10月1日~2021年3月31日までの期間限定のいわゆる特措法です。
ですが、2021年4月1日以降はこの法律の効力がなくなることになります。
そのため、この日以降は消費税法に則って総額表示となります。
つまり、これまでは「消費税転嫁対策特別措置法」のおかげで、期間限定で総額表示をしなくてもよい特例が定められていました。
→消費税課税事業者は、必然的に短期間で何度も価格表示を変更しなければならなくなり、コストや手間がかかるため特例措置がこれまでとられてきた。
それでは、具体的にどのようになっていくのでしょうか?
「総額表示」でなにが変わる?
総額表示になる対象は?
そもそも、商品の値段が表示されているのはお店などの値札だけではありませんよね。
それでは、なにが総額表示になるのでしょうか?
- 商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)
- 店頭における表示
- チラシ広告
- 新聞・テレビによる広告
など、値段が記されているものはたくさんありますよね。
→「消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付け」となる。
つまり、2021年4月1日からは、どんな物であれ値段を記載するのであれば「価格表示=総額表示」にしなくてはいけなくなります。
ちなみに、値引き販売のように「●割引き」「●円引き」など、価格表示が行なわれていない場合は、表示を強制されません。(割引き後の値段を表示する場合は、総合表示になる)
さらにいえば、消費者が商品を購入する際に「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かればいいことになっています。
つまり、個々の商品に税込価格が表示されていなくても、棚札やPOPなどでその商品の「税込価格」が分かるようにしておけば問題ありません。
つまり、総額表示は消費者が購入時に金額を勘違いせずに購入できるようになっていることが大前提です。
*仮に、商品自体に価格が表示されていれば総額表示にしなくてはいけない。
総額表示が表示されていればいい!
表示価格は、総額表示を記載すればいいため国税庁では以下のような例が示されています。
消費税率10%の商品を販売した場合
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
つまり、例えばこれまでのような「税抜価格10,000円のみの表示」は違反となります。
*総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を「四捨五入」・「切捨て」・「切上げ」のいずれの方法により処理してもいい。
→上記の事例で重要なことは、『総額表示の「11,000円」という表示の記載』と言うことになります。
最後に
軽減税率が始まり・レジ袋が有料化され、2021年4月1日から価格表示は「総合表示」に変わります。
事業者としては、新しいレジの導入などが終わり、今度は新型コロナウイルスによる感染症対策の徹底におわれているお店の方ばかりではないでしょうか?
ただ、消費者としては、総合表示になるため「金額が高い!?」なんて勘違いは少なくなるでしょう。
なにより、「8%?10%?」で合計金額を迷わなくなります。
すでに、総合表示に切り替わっているお店もあります。
そもそも、「消費税転嫁対策特別措置法」は消費税が5%→8%へ増税になったときにできた特別措置法でした。
つまり、この特別措置法が2013年に施行されてから終了するまでに、2回(2014年:8% / 2019年:10%)の増税がありました・・・
以前紹介した食品表示の改正もそうですが、身近なところでどんどん法律が変わっています。
知らなかったでは済まないことが多いため、少しずつ知識として身につけるようにしてみてはいかがでしょうか?
参考
しゃかいのぺーじ
→https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/shakai/keizai/04_8_kansetuzei.htm











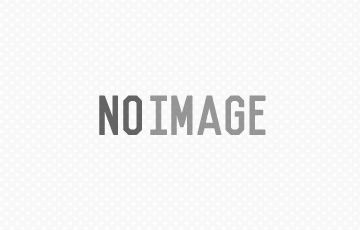



コメントを残す