●この記事では、SNSは消しても罪に問われる可能性があることをお伝えしています。
皆さんは、どんなSNSを使用されているでしょうか?
世界中の不特定多数の人に、一瞬で間単に情報を拡散することができるため注目を浴びようと思えば、使わない手はないですよね。
ただ、以前にも紹介しましたがSNSには注意点があります。
今回は、「消しても意味がない?」についてお伝えします。
→「神待ち」についてはこちらの記事で紹介しています。
→「SNSと写真」については、こちらの記事で紹介しています。
スマホとSNS
いつからスマホはあるの?
私が産まれた頃は、そもそも携帯電話がありませんでした。そんな時代でしたが、私が高校生の頃にはガラケーを持っていることが当たり前になっていた時代でもありました。
これが、約20年前(2005年頃)の話です。
それでは、スマホの普及率をご存じでしょうか?
総務省の平成30年版情報白書によれば・・・
- 2013年:39.1%
- 2014年:44.7%
- 2015年:53.1%
- 2016年:56.8%
- 2017年:60.9%
となり、毎年普及が進んでいきました。
そして、小学生のスマホの普及率は2018年には約46%となっています。つまり、いまや小学生がスマホを持っているのは当たり前の時代となっています。
それでは、そんな当たり前に使えるスマホと言えばSNSを使うのではないでしょうか?
SNSは当たり前・・・
SNSは、今や誰もが複数のアカウントを持っていてもおかしくない時代となりました。
SNSとは、「Social Networking Service =ソーシャル・ネットワーキング・サービス」のことです。
分かりやすく言えば、「インターネットを使って人々と交流できるサービスの総称」です。
- ツイッター
- フェイスブック
- インスタグラム
- ライン
など、いくつも種類がありますよね。
国内外とわず、世界で数億人・数十億人が利用しているため、簡単に誰かとつながることができてしまいます。
例えば、ジャスティン・ビーバーが「ピコ太郎」の動画をシェアしたことで一躍有名になったことは多くの人が知る所ではないでしょうか?
さらに、「SNSを使えば自分が情報の発信者にもなれる」ということになります。

ただ問題は、この情報の取扱いを間違った影響で逮捕される事件が発生している点です。しかも、発信した情報を消したとしても意味がないかもしれません。
発信した情報を消しても意味がない!?
例えば、「上司の奥さんが浮気をしていた!」なんて嘘を、仕事帰りに居酒屋の個室で同僚3人に対してAさんが冗談で話したとします。
同僚もただの冗談だと知っていたため、その後も特になにもなかったとします。
さて、この話が4人だけの中だけで終わっていれば、もしもこの話しを上司が知ろうと思えば、居酒屋でお酒を飲んでいた4人の誰かから直接聞く必要があります。
ただ、この4人がだれにも話していなければ、そもそも上司の耳に入ることはありませんし、仮に耳に入ったとしても実際は録音でもなければ、言った言わないで決着がつかないかもしれません。
そもそも、お酒の席ですのでそんな話しをしたことすら誰も覚えていないかもしれませんが・・・
それでは、これがSNSだったらどうなるでしょうか?
「嘘」を流しただけでは罪にならない?
例えば、嘘を吹聴すれば「名誉毀損」に当たるかもしれませんし、仕事に影響が出れば「偽計業務妨害」などに問われる可能性があることはわかりますよね?
とはいえ、大前提として嘘を流しただけではそもそも犯罪が成立することはありません。
→法律がないため嘘を流しただけでは、「逮捕」や「刑罰」を科せられることはない。
それでは、どうしてSNSで情報発信をしただけで逮捕される事案が発生しているのでしょうか?
問題は、その嘘の結果により引き起こされた損害があるかないかです。
例えば、先程の居酒屋の話しでは、確かに口頭で仲間内だけで上司の奥さんの話をネタにしていましたが、誰にも被害が及んでいませんよね。
それでは、例えばこの嘘を酔った勢いで会社のライングループなどに投稿すればどうなるでしょうか?
もしも、ラインの動作不良などで「誰も気付かない?」なんて、奇跡が起これば当然、罪に問われることはないでしょう。
ですが、その投稿により仕事に支障がでたり、上司夫婦の離婚の原因になるなど、他人に迷惑をかけた時点でその投稿は犯罪行為となります。

嘘を流した時点で犯罪行為!
先程説明したように、嘘を流しただけでは犯罪に問われることはありません。
ですが、ひとたび他人に損害を与えてしまうと、その犯罪行為は「嘘を流した時点で成立」することになります。
つまり、「上司の奥さんが浮気している」という投稿をした時点まで遡ることになります。なにが言いたいかと言えば、損害が出た時点で投稿を削除しても意味がないということです。
さらに言えば、インターネット上は口頭とは違いそれ自体が記録媒体です。すぐに消したとしても証拠は残っていると考えた方がいいでしょう。
その分かりやすい事例があります。
投稿をすぐに消しても意味がなかった事例
2021年1月16日・17日に大学入学共通テストがコロナ禍でしたが予定通り実施されました。
ところが、1月17日の夜にある受験生の「実はコロナ陽性で黙ってたけど試験場のトイレ流すボタンに休み時間の度に唾吐きかけてたからお前ら二次試験受けれないよw」というツイートが話題になりました。
ただし、実際は、その受験生は感染もしていなければ、上記のような行為もしていなかったようです。
とりあえず、大学側は被害届は出さない方向のようです。
それでは、この投稿を受験生はどれくらい後に消したと思いますか?
A.10分程
しかも、「内輪ネタ」として投稿していたことが本人からツイートされていたようです。
「あのツイート10分で消したんですよ…さすがにやばいなあって、、、ネット怖い( ; ; )」「内輪ネタがこんなに拡散してしまっては」
もしも、拡散する前に消したのなら実質的な影響はなかったかもしれませんが、すでに拡散されてしまい後の祭りの状態でした。
ニュースにまでなってしまっているため、大学側に被害が出ていることは明白ですよね・・・
特に、大学入学共通テストは2021年度から新たに始まった、センター試験に替わる大学の共通テストだっため、そもそも注目を集めていました。なにより、コロナ禍ですよね。
普通に考えれば、そもそも注目されないはずがない投稿でした・・・
今回は、被害届が出されない可能性が高いですが、このように実害が出てしまえば「損害賠償」や「刑事罰」などがかかってくる可能性があります。
最後に
SNSを悪用した、さまざまな犯罪が発生しています。
ただ、「騙そう!」という意識がなかったとしても、ネタのつもりで投稿したり、なんとなくリツイートしたりした結果、逮捕された事例もありました。
確かに、魔が差してしまうことはあるでしょう。
ただ、誰かに聞かれても大丈夫な発言か考えてから投稿するようにしないと逮捕されたり、訴えられたりするかもしれません、
特に、「リツイート」はボタン1つで他人の投稿を拡散できてしまいます。簡単にできることは、なにも考えずにやってしまう危険性があります。
例えば、水は蛇口を捻れば簡単に手に入れることができます。それでは、もしも被災してしまい水が配給制になったらどうでしょうか?
節水を心がけたり、水の上手な使い方を考えますよね?
SNSも同じです。
目には見えないだけで、投稿した先にはたくさんの人達がいます。
そして、感じ方・考え方は1人1人違います。
100%安全な投稿は、残念ながら存在しません。
どんな言葉でも、必ず反応する人はいます。
とはいえ、本人に対して直接言えないことを投稿しない方がいいことは、分かっていただけたのではないでしょうか?
参考
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィス:デマを流しただけでも法律で罰せられてしまうってホント?
→https://kanazawa.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3926/
gooニュース:「実はコロナ陽性」共通テスト受験生の虚偽ツイートが拡散、すぐに消してもアウトな理由
→https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-12365.html




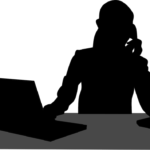





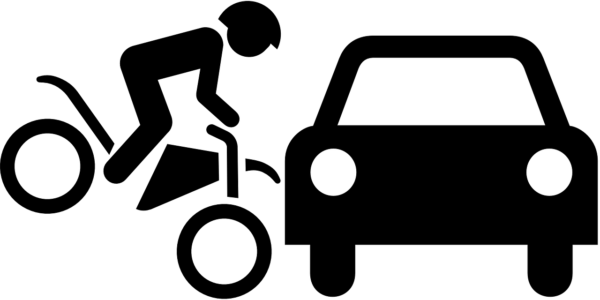










コメントを残す