実際に、私が経験した「なりすまし迷惑メール」の体験から、迷惑メールを罰する法律について紹介しています。
迷惑メールを罰する法律の1つとして、前回「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」についてご紹介しました。今回は、迷惑メールを罰するもう一つの法律「特定商取引に関する法律」についてご紹介します。
●「なりすまし迷惑メール」についてはこちらの記事で紹介しています。
●「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」についてはこちらの記事で紹介しています。
「特定商取引に関する法律」ってなに?
消費者を守る法律(旧:「訪問販売等に関する法律」)
2001年6月に訪問販売等に関する法律が改正されて施行された法律です。みなさんは、「クーリング・オフ」という制度を学校で習いませんでしたか?
実は、この「特定商取引法に関する法律」はクーリング・オフといった消費者を守るためのルールを定めた法律です。つまり、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることが目的。
さらにいえば、「訪問販売や通信販売・電話勧誘訪問販売など」事業者にはさまざまな販売方法があります。ですが、なんでもありでは消費者は搾取されるだけになってしまいますよね。
*電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題に対応するため改正されました。

geralt / Pixabay
特定商取引に関する法律は、こういった契約を締結してしまった消費者を守るための法律なんですが、その中に迷惑メールに対するルールも定められているということになります。→迷惑メールを防止するためだけの法律ではありません。
略称は?
さて、この特定商取引に関する法律はいくつかの略称があります。
- 特定商取引法
- 特商法
といった略称があります。ちなみに、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律=特電法」と略されることがあり「特定証取引に関する法律」と見比べるときに、分かりやすくするために「特電法と特商法」というような使い方をされる場合もあります。
実際、長い名前を覚えるよりこちらの方が分かりやすいですね。
*というわけで以後の記事では・・・・
- 特定取引法に関する法律=「特商法」
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律=「特電法」
で統一します。
特電法の比較から特商法まとめ
この法律の目的は、先程もお伝えしたように「消費者保護と取引きの公正」にあります。そして、規制対象となるメールは、「通信販売などの電子メール広告」となります。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイントより、「特商法」と「特電法」の違いはこのようになります。
| 特商法 | 特電法 | |
| 目的 | 消費者保護・取引きの公正 | 電子メールの送受信上の支障の防止 |
| 規制対象電子メール | 通信販売などの宣伝メール | 自己・他人の営業につき広告や宣伝を行なうための手段として送信する電子メール。 |
| 規制対象者 |
|
|
| *¹オプトイン方式 |
|
|
| 架空アドレスを宛先とする電子メールへの対策 | なし |
|
| 送信者情報(メールアドレス・IPアドレス・ドメイン名)を偽装した電子メールへの対策 | なし |
|
| 電気通信事業者などに対する求め | *²主務大臣は、電子メールアドレスなどについての契約者情報の提供を求めることができる。 | 総務大臣は、電子メールアドレス等についての契約者情報の提供を求めることができる。 |
*¹オプトイン方式とは、「受信者にあらかじめ許可をとってからでしかメールを送信できない」という仕組みのことです。
特商法と特電法を総称して、迷惑メール防止二法とも呼ばれます。また、上記の比較表から分かるように、「特商法」には架空アドレスや送信者情報の偽装にたいする規制がありません。
- 「特電法」は総務省が策定。
- 「特商法」は経済産業省が策定。
→表の一番下「電気通信事業者などに対する求め」で求めることができる大臣が違う理由はそれぞれの省が策定した法律だからです。
*²特商法が「主務大臣」となっているのは・・・
- 農林水産省関係商品市場→農林水産大臣
- 経済産業省関係商品市場→経済産業大臣
商品の中身により、担当大臣が変わるため主務大臣という表現になっています。ちなみに、両省に関わる者は両大臣の共管となります。
特商法の罰則は?
100万円以下の罰金
❶罰則対象となる電子メール広告の提供
- 請求・承諾のない者
- 拒否している者
➋請求・承諾があった旨の記録保存義務違反
1年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはこれらの併科)
同意のない者・拒否者へ送信した電子メール広告において、さらに虚偽・誇大広告や表示義務違反をした場合。
*そもそも、これらの違反行為は行政処分(主務大臣による指示や業務停止命令など)の対象となります。

3839153 / Pixabay
最後に
罰則がどんどん厳しくなり、これまでよかったことがどんどんルール化されています。「規制」とも呼ばれます。
事業者は儲けたい。消費者は被害にあいたくない。どちらも当然の考え方だと思います。あまり規制をかけ過ぎると今度は消費者に商品が出回らなくなるため、規制をかけ過ぎると消費者が最終的に不利益を被ることになります。
規制をかけ過ぎても、緩くても被害を被るのは最終的に消費者です。バランスの取れた規制が進んでいくといいですね。
参考
特定商取引法ガイド
→http://www.no-trouble.go.jp/what/
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
→http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
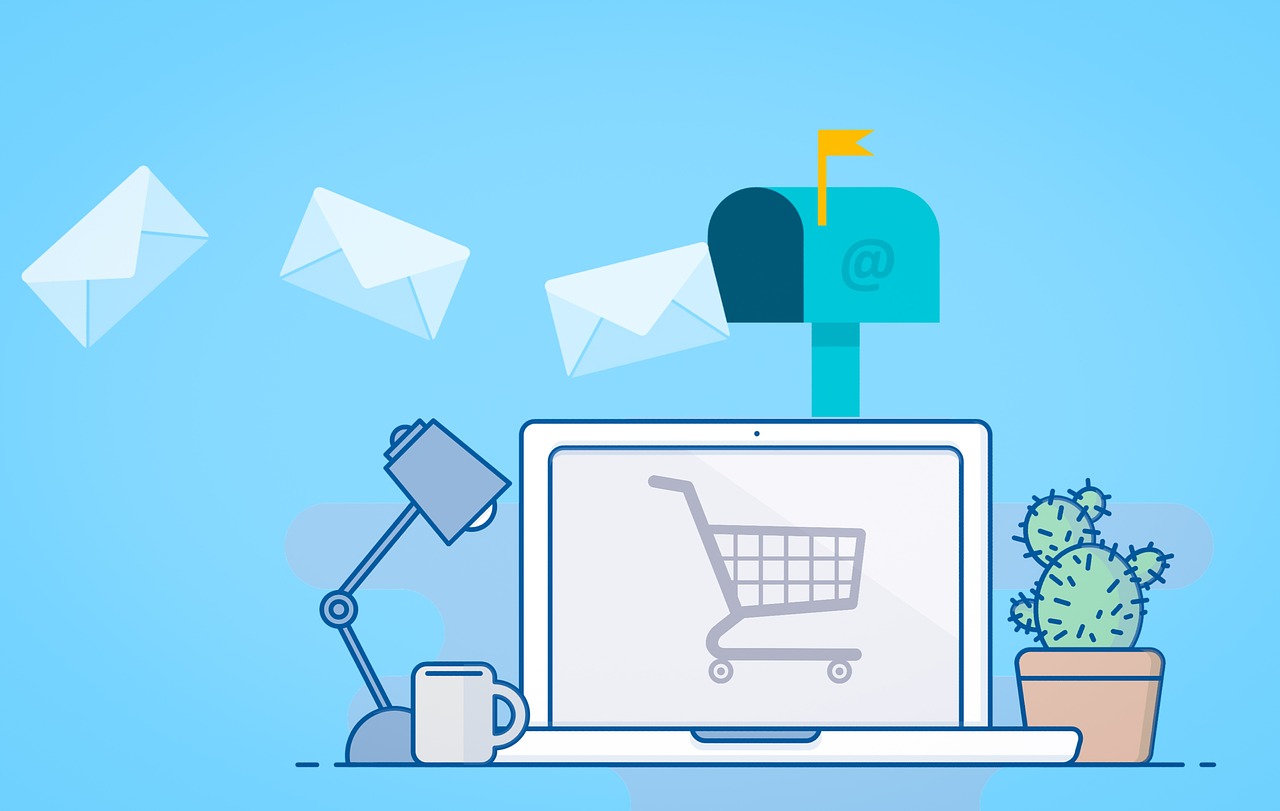















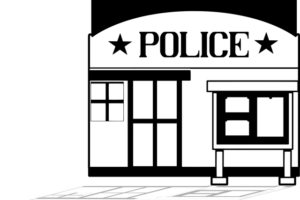




コメントを残す